過去と未来、現在が巡る装置としての盆踊り
隅田川自治β ダイヤローグ⑦
岸野 雄一(音楽家・スタディスト)
弓指 寛治(美術家)
松本 紹圭(現代仏教僧)
夏のお盆の時期、死者を弔うために行われている盆踊りは、弔いだけでなく地域の紐帯やコミュニティの基盤をも担ってきました。コロナ以後の社会における盆踊りの位置付けを問い直すため、音楽家・スタディストの岸野雄一さん、美術家の弓指寛治さん、現代仏教僧の松本紹圭さんに、生と死、過去と現在と未来をつなぐものとしての盆踊りとは何かを語っていただきました。
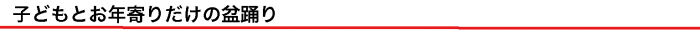
—— 『隅田川怒涛』では新型コロナの影響で実現が叶わなかったプログラムの一つに、盆踊りがありました。地域のつながりやコミュニティを再考する装置である盆踊りを、現代において改めて慰霊と鎮魂の役割を持ちうるように実装できればという思いがありました。このコロナ禍の最中に盆踊りのあり方について議論したく、今回は、それぞれに盆踊り、生と死、信仰について向き合っているみなさんとお話ができればと思っています。
岸野雄一(以下、岸野):子どもの頃から、近所の盆踊りを巡って、どの曲が何時頃にかかったかを調べ、自分なりのリストをつくっていました。盆踊りと平行して色んな歌謡曲やロックなどの音楽を追いかけていたんですが、なぜかそういった音楽は盆踊りでかからず、決まりきった曲ばかりが流れ、結果、小学生以下の子どもとお年寄りばかりという形になり、次第に地域で盆踊りが廃れていきました。
インターネットが登場して、趣味の話を遠くの人とできて、それで人間関係は良いんじゃないか、と思ったけれども、2011年の東日本大震災以降、地縁というものを改めて考えるようになりました。いざというときに、趣味が合わない人ともなんとか折り合いをつけていかなくちゃいけません。その地縁の見直しに、盆踊りは大事だと思いつつも、地縁や盆踊りは町内会と結びついてて、なかなか思うようにいきません。自分たちの力で、地縁でさまざまな問題に対して個別に解決していくなかで、民主的に勝ち取っていけるようなモデルケースをつくりたいな、と思っています。
—— 弓指さんは、お母さんの自死をきっかけに作品を発表されています。「あいちトリエンナーレ2019」における作品展示では、生と死や死者と生者との関係をテーマにした作品づくりに取り組んでいました。今回も、本来であれば盆踊りの空間づくりをご一緒したいと思っていました。
弓指寛治(以下、弓指):2015年に母が死んだ時、お坊さんに、自殺の是非について質問したんです。そうしたら、仏教的には自殺は良くないことだと言われ、母の死を仏教的に否定されたような気がしました。地元が三重県の伊勢なので、お参りならいいだろうと思ったら、親戚から身内が亡くなって1年間は身体が汚れてるからお参りはダメだ、と言われ、神様にすがりたいのにその入り口にさえ立てなかったという経験をしました。お医者さんも助けてくれるわけではなく、宗教的にも否定された気がその時はしました。母が亡くなった後、棺桶に鳥のイラストを入れた時に、ふと、母親のために絵を描けばいいのか、と思ったんです。そして、自分以外にも、身内が自殺して苦労している人もいるけれども、みんな生きてるし、無理に死んだ人を乗り越えるような形で死者と向き合わなくても、悲劇的な死に方をした人をそのままにせず、一緒に生きていけるような形があるのかなと思い、美術家としての活動をするようになりました。
実家では、祖母が私の面倒をよく見てくれました。そんな祖母が亡くなってすぐに母が死んだこともあって、その祖母が好きだった盆踊りを思い出し、盆踊りの絵を描いたことがきっかけで、死者と生者の関係に気づかされました。自分の身に起きたことに反応しながら、たまたま自分は死者にまつわることやそこから転じて生きることを考えるようになっていき、身内だけでなく、社会のなかで起きている事件や事故にも目を向け始めています。自分なりに、死者に対して生者が何ができるか、ある種の慰霊のような気持ちを込めています。
—— 最近は、どのような活動をされているのですか?
弓指:被災されたとある地域で、慰霊と関連した作品をつくっています。そこでは広い公園に木々が植えられていて、ボランティアの方たちが森にする活動をしながら、被災の記憶を語り継いでいっています。その地元の方々の声を聞くと、何もない広い公園なのに街のイメージが記憶から浮かび上がってくるんです。そんな場所だからこそ、画家として絵を描いて作品を残したいと思っています。過去と未来は、言葉で分けることができますが、実は全部つながっていて、現実は過去に戻れないけれども、作品や頭の中は、過去も現在も未来も行き来することができると考えています。
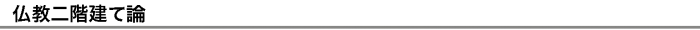
松本紹圭(以下、松本):お坊さんをしていると、死者を弔う数々の場面に立ち会います。しかし、仏教の原点であるブッダの教えに立ち返ると、仏教とは、自身の苦しみを乗り越え、どう生きるかを問い続ける「道」でもあります。歴史的な経緯から、日本仏教は弔いの機会が特に強調されてきましたが、世襲でお寺を継ぐ身ではない私としては、一生をかけて死者を弔いたいという気持ちより、「仏道」、つまりいかに生きるかに関心があって僧侶になりました。
仏教という大きな看板には、様々な要素が詰め込まれています。そこで、日本のお寺を「二階建て」構造として見てみると、日本仏教が果たしてきた機能や役割を捉えやすいです。一階は、過去を生きた死者へと意識を向ける「先祖教」、二階は、今を生きる人々がそのあり方を問う「仏道」を担っているとみています。最近ではマインドフルネスの流行もあって、自らの人生や社会のあり方に悩み、「仏道」に向き合いながら二階に足を運ぶ人が増えてきました。一方、先祖を弔う法要や御墓参りなど、家制度と紐付いてお寺の経済を支えてきたのは一階の「先祖教」です。「先祖教」を大切にして過去と向き合うと同時に、それらを「今、私が生きること」とどう結びつけるかを、私自身考えてきました。
そんな時に、イギリスの思想家ローマン・クルツナリック氏の著書『The Good Ancestor』に出会いました。本書は、私たちはよき祖先になれるか、という問いを投げかけます。やがては、私たちが祖先となる未来がやってきます。仏教が過去に目を向けるとき、そこには同時に未来への橋が架けられていて、私たちは、その全体の中に組み込まれた今を生きています。死者を思うことは未来を思うことであり、それは、今、私自身がどう生きるかということでもあります。この本には、長い時間軸と広い視野で今を捉える仏教に通じる視点があって、「この本を翻訳したい!」と思ったんです。

松本:私が翻訳した『グッド・アンセスター』では、「ancestor」という単語を、家系の縁に限定されがちな「先祖」ではなく、より開かれた過去への縁を意味する「祖先」と訳しています。そこには、お寺文化の反省もあります。お寺はこれまで、弔いの方法においても、檀家制にみられるお寺と人々との関わり方においても、主に「家」制度に基づいて機能してきました。「出家」した身でありながら、お坊さんの多くが世襲でもあるように、「家」にこだわってきたのはお寺自身かもしれません。しかし、今は結婚しない人、結婚しても子どもを生まない人などいろいろな生き方があります。そんな時代に、「家」を前提にして仏教が成り立っていることに、私は疑問を感じています。
近年のコロナ禍で、お葬式も身内だけで執り行われることが通常になり、弔いの機会を持てないまま、大切な人の死に出合う「曖昧な喪失」が増えました。人には、関係性の数だけ顔があります。平野啓一郎さんはこれを「分人」と表現されています。これだけ生き方が多様化するなか、様々な顔、様々な分人の集合体で個人が形成されているのであれば、家族というのも一つの関わりに過ぎません。あまりに「家」を重視することによって、他の分人が成仏できず、弔われる機会もなくなっています。お寺は閉じられた「家」を基軸にするのではなく、誰もが誰もを弔えるような、開かれた縁へと発想を転換することが必要だと感じます。
文化や風土など、血縁に関係なく、先人からの恵みを受け取った私たちは、それを手渡していく時も、自分の直接的な子どもや孫だけでなく、開かれた無数の縁のうえに繋がる未来世代へと恵みを残すことができる。そういう意味で、あえて「祖先」という言葉を使っています。


写真:松本さんの活動の様子
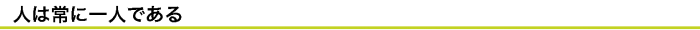
—— 盆踊りは、死者への弔いの意味だけでなく、地域の人たち同士が集まって準備をし、参加した人みんなで踊るという場所でもあります。
岸野:盆踊りは、ただ踊るだけでなく、あるときは男女の交流の場として扱われたり、地域によっては徹夜で踊ったり無礼講で身分を外したりする場でもありました。もちろん、お盆のときに死者に対して、自分たちが元気な姿でいることを見ていただきましょうという考えは、基本的なものとしてあったと思います。
一方、誰かが亡くなった時、亡くなった直後はそうでもなかったのに、ふとした時に思い出し、涙を流すことがあります。そうした体験は誰しもがあるはずです。盆踊りは、そうした死者への思いを想起させる装置にもなりえるように思います。
—— お祭りの喧噪の中、ふと冷静になって、盆踊りの渦中の中から離れることで、違う世界が見えてくることがあります。最近では、音楽ライブが一体感を体感するための役割を担ってきたように思いますが、それとは違う次元のものが盆踊りにはありそうです。
岸野:私は、盆踊りをすればみんなが一つになれるとは考えていません。盆踊りは、みんなそれぞれがある意味で一人になれることの崇高さがあるはずです。
松本:現代の仏教者、スティーブン・バチェラー氏は『The Art of Solitude』という本を書いています。”Solitude”とは、”Loneliness”でも”Isolation”でもなく、一人だけれどネガティブでもポジティブでもないプレーンな状態、ただ一人でいるということを表します。つまり、人は生まれてくる時も死ぬ時も一人であるように、その存在は徹底的に一人であるということです。みんなが一つになるのはあり得ないという、絶望的なある種の孤独を心の底から知っている者同士の足元にこそ、つながり合える地平があると気づかされます。

—— コロナ以前は、踊ることの楽しさから、若い人たちの間で盆踊りブームもありました。
岸野:もちろん、踊ることが楽しくて浮かれるのも大事です。踊ってる時、踊りがまだ身体に入っていない時は、曲と合ってるかが不安で演者の語りが入ってこないけれども、何時間もやってると自然と踊りが身体に入って半ば自動化し、自分が自分でなくなるような一種のトランス状態に近くなります。踊ってるんだけれども、どこか気持ちは落ち着いている。そうすると、次第にお念仏が頭に入ってくる時があります。ただ座って聞くんじゃなくて、踊っていて自分が自分じゃなくなる感覚の時に入ってくるんです。
一方、そういう体験は悪用されたら怖いけど、怖いと思ったらすっと冷めてしまう、そんな感覚を持っています。盆踊りは、神妙になってはいけないが、真面目に踊らないとその魔法も起きません。
弓指:儀式みたいになってしまうと良くないですよね。楽しめない。楽しく踊ることで没入していく感じがあります。
松本:中島岳志さんの『思いがけず利他』という本で、利他性について書かれているのですが、そこでは、利他性とは純粋なもの、言い換えれば「思いがけず」生じてしまうものであって、そこに意図が入ると利己が混じって純粋性は失われ、利他ではなくなると指摘しています。これは國分功一郎さんによる「中動態」の概念にも通じます。盆踊りで言うと、踊っているのか踊らされているのか分からない状態のことですね。ある意味、それは開かれているような状態でもありそうです。
弓指:絵を描くという行為もそうした性質がありますね。自分で描いているのか描かされているのか。もちろんテーマを持って描こうとしてるんですが、当然その通りにはいかない。想像してたものと、腕を通して出力されたもののイメージは違います。自分が描いてるのがよく分からなくなり、気晴らしに何気なく描いたものが、実は当初思っていたものと違う方向に完成の道筋があった、ということは多々あります。
私は、展覧会を中心に作品を発表しています。作品をまとめて鑑賞してもらい、その鑑賞体験そのものを設計しています。しかし、その展覧会をするための絵を描いてる時は、その一枚に向き合っていて、それがどのように仕上がるのか、着地は見えていません。展覧会という空間表現のような全体性と同時に、絵一枚の個別性に向き合いながら作品をつくる、その両方が矛盾しながらも同居している感じです。

写真:弓指さんの制作風景
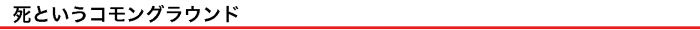
—— 盆踊りを地域で行う過程で、さまざまな関係者との調整やすり合わせなど地道で大変なことも多々あります。
岸野:そうですね。いわゆるメンツをどう立てるか、誰に話をつけにいくかといった物事の順番も、学びながら少しずつ分かっていきました。ただ話を通していれば済むわけではなく、きちんと関係をつくって、相手が望んでいることを何か手助けできるかを考え、認めてもらうことが大切です。
松本:私は、盆踊りを通して、この国のデモクラシー、民主主義を再構築することができるのではないかと思っています。今、コモンズのあり方が問われています。それは、都市の話だけでなく、田舎も同じです。個々人同士のつながりもどんどん弱くなり、中間共同体も空洞化しているのを本当に感じます。価値観が多様化すると、隣の人が何を考えているのかがわからない。すると、何をコモングラウンドにしたらいいのかが分からなくなります。
そうしたときに、死は、すごく強烈なコモングラウンドになりうるのではないでしょうか。死は、誰しもに訪れ、すべての人に共通するテーマです。盆踊りは祝祭的でもありながら、その中心に死があり、生者と死者が出会い、混じり合う。死というコモングラウンドが、デモクラシーの基盤になって、その拠点の一つにお寺がなれば素敵だな、と思います。
岸野:確かに、死をコモングラウンドにするという意味で、盆踊りはその基盤になりえそうです。一方、常に私が意識しているのは、とにかく亡くなった方を利用しないということを気をつけています。
松本:そうですね。グッド・アンセスターも、誤読されることもありえます。全然あらぬ方向にそれが利用されないようには気をつけたいです。
岸野:台湾のデジタル担当大臣であるオードリータンさんがおっしゃっていましたが、民主主義のためには亀裂が大事で、亀裂があるから光が差し込む、だから亀裂を恐れてはいけない、という言葉に励まされました。盆踊りの準備をしていくと、必ず亀裂が起きます。みんなそれぞれ盆踊りに対する考えがあって、お祭りはいろんな人が関わってはじめて成立するものです。盆踊りに限らず、地域でなにかをやると問題が起きます。そのときに「しめたものだ!」と思います。問題をフックに、じゃあみんなでどうしていこうか、と議論しやすくなります。インターネットのような同じ趣味を持って好きなことやってる人たちの集まりではないからこそ、そうしたいろんな人たちをしっかりと受け入れていくことが大事で、難しいけど面白いし、そこが多様性なのではないか、と。


写真:岸野さんがプロデュースするDJ盆踊り
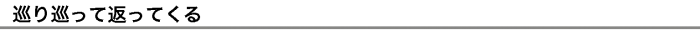
岸野:弔いなどの儀式性をはらんでいる盆踊りは、踊るという行為だけでなく、そうした深い考えが背景にあるということを、盆踊りに参加している人たちにどう周知していくとよいのでしょうか?
松本:私個人としては、特に周知しなくて良いと思います。ただ、舞台設定や感じる人が深掘りしていけば理解してもらえるような仕掛けは必要です。表面的には、屋台もあって楽しそう、というくらい。よくよくみると、人それぞれに、いろいろな深さに気がつくというくらいです。
弓指:バランスは大事ですよね。扱っているものは切実であっても、儀式的なものに絡め取られてしまわないように、私も作品づくりで気をつけています。作品の裏側にある真意を無理に表に出さなくても、誰であってもそのことを知らなくても楽しめるようなものに、盆踊りもあってほしいです。
松本:私は、もはや仏教はアンビエントブディズム、つまり環境に埋め込まれたものではないか、とも思います。意識せずとも、日常の中にすでに仏教があり、触れている。祈りの象徴やアクセスポイントとして、お寺があり、仏様がある。そんな象徴的な場に人々が集い盆踊りに身を任せる、その体験そのものをたどっていくことで、知らぬ間に救われていたような状況がつくれたらいいな、と。
岸野:たどっていける仕掛けはたしかにあるとよいですね。
松本:仏教における「供養」とは、気持ちを供えたり、手向けたりするという意味です。もう一つ重要な言葉として「回向」、つまり死者の成仏を願った供養が、巡り巡って自分に還ってくるというものです。盆踊りも、亡くなった方々に気持ちを向けるとともに、その功徳が自分や家族、他の人たちに渡っていく、そんなことが起きている空間なのではないでしょうか。
弓指:盆踊りが集まる場でありながら、それぞれの人にとって、過去や未来とつながり、思いを馳せられる場所なのかもしれません。
松本:盆踊りは、踊る私たちを、亡くなった人の供養のために手向けつつ、未来の人たちにも振り向けていこう、ということにもつながるはずです。祭りに連なる人たちも、儀式的な意味を意識しなくても、踊りに参加したら実は自動的に「回向」をしている。そうした祝祭空間としての盆踊りのあり方を再考できるとよいかもしれません。
取材:清宮陵一、小出有華(NPO法人トッピングイースト)、編集:江口晋太朗(TOKYObeta.Ltd)
カバー写真:松本紹圭さんが所属する東京神谷町の光明寺で行われた鼎談
——————————————————————————————————————————————
岸野 雄一
勉強家(スタディスト) 東京藝術大学大学院 ・非常勤講師、美学校音楽学科・主任。第19回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門大賞受賞。ヒゲの未亡人、ワッツタワーズ、スペースポンチ、流浪のDJ、ほか。
弓指 寛治
1986年三重県出身。東京都拠点。「自死」や「慰霊」をテーマに創作を続ける。名古屋学芸大学大学院修了後、学生時代の友人と名古屋で映像制作会社を起業。代表辞任後上京、ゲンロンカオス*ラウンジ新芸術校の第一期生として学んでいた2015年に、交通事故後で心身のバランスを崩していた母親が自死。出棺前に「金環を持った鳥のモチーフ」が浮かび、以後制作される多くの作品で繰り返し登場する彼の表現の核となっている。2021年より「満洲国」を軸に過去の戦争について考えるためのプロジェクトを開始。
松本 紹圭
1979年生まれ。現代仏教僧。東京大学哲学科卒。インド商科大学院でMBA取得後、住職向けのお寺経営塾「未来の住職塾」を開講し、2022年現在、9年間で700名以上の宗派や地域を超えた卒業生を輩出。著書多数。邦訳書に『グッド・アンセスター わたしたちは「よき祖先」になれるか』(あすなろ書房)。noteマガジン『松本紹圭の方丈庵』、ポッドキャスト『Temple Morning Radio』を配信中。


